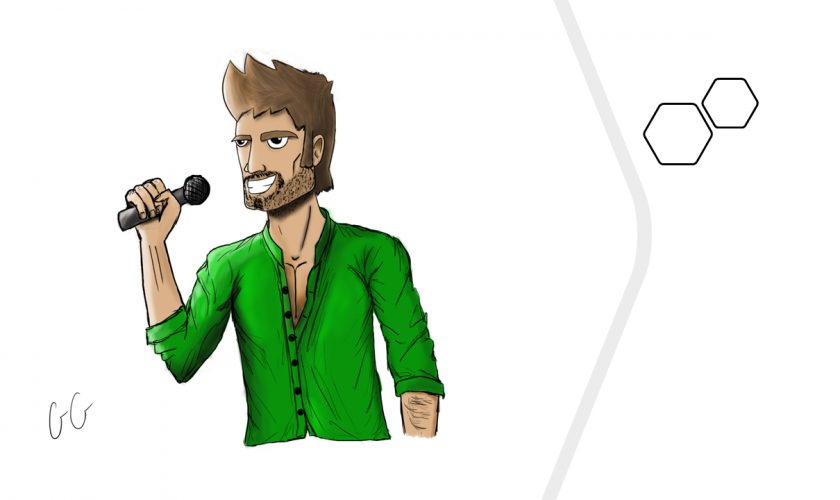最近、小林克也さんがホストを務める『ベストヒットUSA』の誕生40周年の記念番組を見た。
81年に誕生した「洋楽」専門の番組で、その翌年に上京した大学生にとって、これが見れるだけで東京に出てきたかいがあったと思ったものだ。
ミュージックビデオというものの存在もこの番組で知った。
当時はまだビニールレコードの時代で値段も高かったが、高校生くらいの時から貸しレコード屋という業態が現れてとてもありがたかった。
ジャケットからそっとレコードを取り出し、ターンテーブルにセットし、針を落としてパチパチとノイズを聞きながら、どんな音が聞こえてくるか、いささかの緊張を持って耳を澄ます。
どうだ参ったか、といったアーティストの作品に圧倒されることを期待しつつ。
40年の時を経ても小林克也さんの渋い声は健在だったが、ゲストのジョン・ボン・ジョヴィ氏は油が抜けていた。
今や、曲を聴くだけならYouTubeで十分だ。
それでもファンは、曲を買ったりグッズを買ったりしてお金を落とす。ライブコンサートのチケットは争奪戦である。
SNSでファン同士が交流し、誰かの感想がネット上でエコーし、他の人の感想を巻き込んで雪だるまのように大きくなり、時には炎上した火の玉になって情報が拡散していく。
ファンは作品に圧倒される受け身の存在ではなく、積極的にアーティストのマーケティング活動に関わることを望む。
K-POPはそのようなムーブメントを仕掛け、育て、さらにその上に乗っかることで、大きな産業に発展していった。
アーティストは楽曲コンテンツの制作者であることに変わりはないが、楽曲自体はあくまでファンの話題のきっかけであり、ファンを結びつけるメディアと考えてもよいのではないだろうか。
こういったコンテンツのメディア化は、芸能分野だけではなく、いたるところでヒントになるように思う。
モノやサービスの作り手は、どうしても圧倒的なコンテンツで顧客を虜にし、他社を凌駕したいと思ってしまう。
そういう「上から目線」的な発想では顧客の思いとのズレも生じるだろうし、そもそもそんなことは難しい。
モードをけん引するという使命に燃えたアパレルの苦境は、こんなところに理由があるのではないか。
消費者を主役に立て、彼・彼女らが集える場づくり、きっかけづくりが求められているのだと思う。
「顧客ニーズへの適応」は誰もが考えることだが、理想像が「上から目線」であることで、顧客と目線を合わせられないことが多いのではないか。
一方で、売上を上げ、利益の取れる製品・サービス(=コンテンツ)を開発しないとビジネスは成り立たない。
しかし、いきなりそこを目指すのではなく、コンセプトや世界観でファンのベースをつくることをまず考える。
ファンが集い、話題にできるような製品やサービスをまず考える。
それがメディア発想のビジネスだと思う。
きれいな言葉で飾られたコンセプトは、知らず知らずのうちに「お前たちに教えてやる」という上から目線になる。
必要なのは、ファンが素直に共感できる、弱さやかっこ悪さも混ぜ合わせになった、生身の人間から生まれた本物の世界観。
リーダーに問われるのはそれだ。